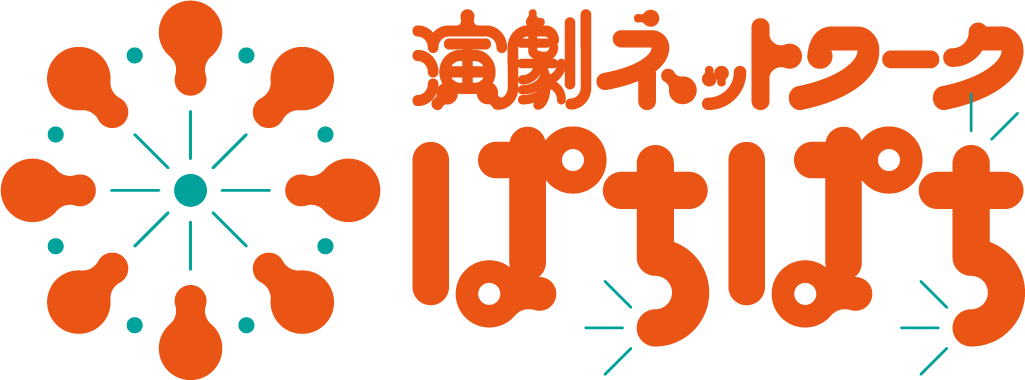「あなたが演劇とのより良い付き合い方を見つける」を目的に活動する演劇ネットワークぱちぱちでは2024年も様々な企画に取り組みました。
その中から、「まじめに演劇をする場」通称『#マジゲキ』という、高校生と演劇を作る企画を紹介します。演劇に興味のある高校生を対象に、25歳以下の個性豊かなぱちぱちメンバーとベテラン俳優・演出家・ダンサーがワークショップを実施して、それを踏まえた演劇公演を上演する「プロジェクト型」の企画です。
この記事では、演劇ネットワークぱちぱち総合ディレクター中込遊里が考えた「プロジェクト型」であるからこその『#マジゲキ』の価値について記載します。
本記事の目次
- 『#マジゲキ』ってどんな企画?
1-1. まじめに演劇を考える場(ワークショップ)
1-2. まじめに演劇を上演する場(公演) - プロジェクト型の創作スタイル
- 劇団とプロデュースチームの違いとは
- プロデュースチームでの創作における価値は「新鮮な表現」なのか?
- 自分の価値観を言葉にするための栄養
『#マジゲキ』ってどんな企画?
演劇に興味のある高校生とぱちぱちメンバー(演劇を続けたい思いのある18歳~25歳)が、俳優や演出家の講師の指導のもと、「演劇の持つ豊かさ、懐の豊かさを知る」「自身になかった指標を見つける」を目指す企画。
2024年は「まじめに演劇を考える場」「まじめに演劇を上演する場」の2シーズンに分けて、ワークショップと演劇公演を開催した。
まじめに演劇を考える場(ワークショップ)
5月3日~5日と7月28日に開催した。
ぱちぱちメンバー・大橋里乃さんによるレポートはこちら。
真面目に演劇を上演する場(演劇公演)
高校生がインド神話『ラーマーヤナ』に挑戦!
「まじめに演劇を上演する場」では、2024年12月21日に「ぱちぱち版文化祭」のようなイベント『わーわーフェス』に参加して公演を開催した。
演出は、2023年に引き続き早坂彩さんが担当して、インド神話の『ラーマ―ヤナ』を45分ほどで上演した。




高校生9人、ぱちぱちメンバー6人が出演とスタッフで活躍した。公演は1ステージ。ほぼ満席で、78人の方にご覧いただいた。立ち見でご覧いただいた方も!
アフタートークも行った。




▲右が俳優の武井希未さん。隣が演出の早坂彩さん。
30分ほどのアフタートークでは、お客様より質問や感想をいただき高校生や講師のみなさんが返答した。
「なぜ(日本ではあまり有名ではない)ラーマーヤナを選んだのか」という質問をいただいて、「分からないもの、身近ではないものにこそ挑戦する」という意義を、演技指導の武井希未さん、演出の早坂彩さんがそれぞれ応答した。本企画の目的「自身になかった指標を持つ」について出演者も観客の方も考えるよい時間だった。
稽古の様子

▲ダンサーの木皮成さん、演出の早坂彩さん、中込遊里、ぱちぱちメンバーのみんなと高校生。『ラーマーヤナ』の理解をしつつ身体を動かす稽古の日。
10月から劇場入りまでにおおよそ11日間稽古を行った。
稽古前の時間では、ぱちぱちメンバーのリードによるアップ(身体をほぐしたりして稽古にスムーズに入れるようにするもの)を行い、親睦も深めた。
演技指導の平川さん、木皮さん、武井さんにも様々な角度から創作に関わっていただいた。
一緒に基礎訓練をしたり、動物の動きを研究したり、炎が燃え盛るシーンの演出方法のアイディアを出し合ったりと、稽古場は活発だった。

▲平川さんリードで基礎訓練を行う。
高校生の意見
稽古・本番に参加してくれた高校生の意見は好評だった。
公演終了後に回答してもらったアンケートでは「あなたにとっての演劇の幅が広がりましたか」という質問に、5段階評価で「5」と回答したのは9名中5名だった。残り4名も「4」だった。
また、印象に残ったことについては以下のような意見が得られた。
「講師の平川さんや吉田さん(舞台監督)に教わったことが的確で効果を感じられた」
「去年もマジゲキに参加して同じことを感じたが、いつもの部活とは違って大学生やプロの方と一緒に作ることが楽しく学びが多い」
「みんなから次々と色々な案が出る稽古。また、講師の木皮さんから教わった動物の演技が印象的だった」
「リハーサルが長くて、演劇部とは違って驚いた」
「台詞がこんなにない劇は初めてだった。身体表現を吸収できた」
ぱちぱちメンバーの意見
一方、ぱちぱちメンバーからは、以下のような、今後の事業に活かすための具体的な意見が得られた。
「高校生と共通の課題に取り組むことでコミュニケーションが取りやすくなった」
「高校生を主役にする事業にするためには、もっと工夫が必要なように思う。たとえば、今回はぱちぱちメンバーがフォローをしすぎたのではないか?」
プロジェクト型の創作スタイル
演劇ネットワークぱちぱちは劇団ではないので、ほぼ100%「プロデュースチーム」での「プロジェクト型」になる。
つまり、公演のために集まった「初めまして」のチームで、期限内に成果を出す=公演を成功させるという創作スタイルだ。
#マジゲキ『ラーマーヤナ』は、関わる人の多さという点で、ぱちぱちにおいても代表的なプロジェクト型の公演といえるだろう。さらに、高校生、ぱちぱちメンバー、演出家、俳優、ダンサーという多岐にわたる立場の方が集まり創作をする複雑さを持つ。稽古場を提供してくださるなど支えてくださった演劇部の顧問の先生や、主催の八王子市学園都市文化ふれあい財団の職員の方も制作に深く関わっている。

▲出演・スタッフのぱちぱちメンバーと高校生の他、財団の職員さん、講師のみなさんの集合写真。
私自身は劇団文化の中で演劇を作ってきた。学生時代には「演劇組織 夜の樹」という劇団に8年間所属して演劇を学んで、自分の劇団「鮭スペアレ」も立ち上げて20年になる。
プロジェクト型の演劇公演には、八王子の演劇事業でほぼ初めて関わるようになったといっても過言ではない。
そもそも、プロデュースチームで作られるプロジェクト型の公演と劇団での公演では何が違うのか。
劇団とプロデュースチームの違いとは
私がまず思い浮かべたことはこれだ。
劇団はまとまりやすい一方で新しい風が吹きにくい。
プロデュースチームは同じ目的に向かうのが難解な場合が多い一方で新鮮な表現方法を得やすい。
試しにChatGPTにも聞いてみた。だいたい同じ答えだった。少し長いが全文引用する。
劇団のメリット:
1. **安定性と結束力**: 劇団に所属する固定メンバーはお互いをよく知り合い、信頼関係が築かれています。これにより、演技や舞台裏の作業での連携がスムーズに行われることが多いです。
2. **長期的な成長**: 劇団は長期的なビジョンや作品の開発が可能です。メンバー同士が共に成長し、演劇のスキルや演技力が向上することが期待できます。
劇団のデメリット:
1. **柔軟性の欠如**:劇団内での慣習やルールに縛られることがあり、新しいアイデアや異なるアプローチが取りにくい場合があります。
2. **人員確保の課題**: 劇団メンバーが固定されているため、特定の役割やスキルが不足している場合、適切な人員を見つけることが難しいことがあります。
プロデュースチームのメリット:
1. **柔軟性と多様性**: 公演毎に最適な俳優やスタッフを集めることができるため、作品ごとに最適なチーム編成が可能です。
2. **新しいアイデアと刷新**: 多様なバックグラウンドや経験を持つメンバーが集まることで、革新的なアプローチや斬新な演出が生まれやすいです。
プロデュースチームのデメリット:
1. **チームの一体感の欠如**: 毎回異なるメンバーで構成されるため、連携や信頼関係の築き直しが必要となる場合があります。
2. **費用と時間の管理**: 毎回新たなチームを構築するため、調整やリハーサルの時間が限られていることが費用やスケジュールの管理を難しくすることがあります。
まず劇団のメリットとデメリットを見ると、劇団文化で育った私個人の感覚では「その劇団によって違うよな」とは思う(当たり前だけど…)。
ただ、どの劇団であっても大きく共通する特徴はある。「価値観の近い人の集まり」ということだ。そのことがメリットにもデメリットにもなる。
よくも悪くも、活動する期間が長ければ長いほど「自分たちにとっての当たり前」で満たされていく。
プロデュースチームでの創作における価値は「新鮮な表現」なのか?
さて、プロデュースチーム(プロジェクト型公演)はどうか。
ChatGPTの言うとおり「作品ごとに最適なチーム編成が可能」なのは特長だと思う。高校生とベテラン俳優、個性豊かなぱちぱちメンバーが集まって創作するのは、『#マジゲキ』だからこそできることだ。
ただ、「革新的なアプローチや斬新な演出」というメリット、つまり「新しさ」「新鮮さ」に光を当てるならば、必ずしもそうとはいえないと思う。

私は2017年から高校生と一緒に演劇を作り始めた。『#マジゲキ』のような学校外での企画において常に目指していることは、演劇部内の活動では得にくい創作を高校生に体験してもらい、「こんなのも演劇なんだ」「もっといろいろな演劇を観て/つくってみたい」と思ってもらうことだ。
学校内の演劇部もどちらかというと「劇団」に寄った創作スタイルだろう。
メンバーはその年ごとに入れ替わりはするものの、先輩が伝える練習方法や顧問の先生が作った空気感は引き継がれる。
さらに、高校演劇ならではの制限が多い。公式の大会でいえば上演時間は60分以内、リハーサルの時間はほぼなしで装置や照明にはそこまでこだわれない、演出は顧問の先生か生徒に限られる、など。
その制限がデメリットというわけではない。制限があるからこそ良い作品が生まれることは多くある。だとしても、他にもいろいろな演劇があることを知ってもらいたい。そのために、学校外で、様々な知識や背景を持った人たちで刺激しあいながら創作する機会を作っている。
さて、その創作の価値は「新しさ」なのか?
自分の価値観を言葉にするための栄養
経験や価値観には個人差があるため、同じものを見ても「新しい」と感じるかどうかは人によって違うはずだ。だからプロジェクト型公演の価値を「新しさ」と捉えると曖昧になりすぎないだろうか。
劇団と比較して、多くのプロジェクト型(プロデュースチーム)に共通する特徴はなんだろう。
それは、『#マジゲキ』のように、経験や背景の違いがあるからこそ異なる価値観を持つ人たちが集まるということだと思う。その創作を通しての出会いがプロジェクト型公演の価値を作る。
あなたにも経験はないだろうか。誰かと意見が食い違って初めて自分が大切にしているものがわかったこと。
私が今でもよく思い出すのが、劇作家や演出家の友人たちと集まって、劇評(だったかな…なにせ10年以上前のことなのだ)をそれぞれ書いた時のこと。私が「イデア」という言葉を使ったところ「そんな言葉使うんだね」と驚かれたことがあった。
大学の恩師がよく使っていたので当時20代の私はふつうに使っていた。劇団の仲間ともふつうに使っていた。さらに思い込みの強い私は、演劇を語る上で割と一般的な言葉なのだろうとすら思っていた(あまりにも思い込みの強い自分の性格に驚く)。

▲7月のワークショップの集合写真。『ラーマーヤナ』以外のメンバーも一緒に創作した。
もうひとつ、大学の演技論(実技)の授業中のこと。俳優・演出家の串田和美さんが先生だった。いまだに覚えているのが、「おれ、泥棒ってなんか好きだな」と串田先生がつぶやいたことだ。
(犯罪者である)泥棒が演劇では魅力的になることもあるのか!と真面目な私は考えたのかもしれない。なにより、串田先生のチャーミングな表情に、理屈抜きで、泥棒には私がまだ知らない魅力があるんだなあ、と素直に受け取ったことをよく覚えている。
家族や友人同士においても様々な似た経験があるが、自分の価値観を知るきっかけとなった強烈な体験は、作る/観劇するを問わず演劇関係が大半を占める。関わる人の価値観やこれまでの経験が直接的に舞台を作るからかもしれない。
だから、価値観が異なるメンバーで創作に挑むプロジェクト型ならではの価値は「自分の価値観を知るきっかけになること」ではないだろうか。もっといえば、「自分の価値観を育てるための栄養」が『#マジゲキ』の創作かもしれない。

プロジェクト型は短期間で解散する。短期間だからこその出会いがある。
特に『#マジゲキ』は一期一会だ。高校生はあっという間に(と、私はいつも感じている)高校を卒業して、ぱちぱちメンバーは自由に様々な場所で活躍する。多忙な講師のみなさんが再び一堂に会するのは難しい。
高校生の未来を思う。この先の長い人生で、何度「あなたはどんな人ですか?」と問われることだろう。大学でも職場でも、「あなたはどんな人ですか?なにができますか?なにをしたいですか?」の問いの連続だ。それに答えるには、自分の価値観を知り、言葉にして(自分にも他者にも)伝え続けるしかない。
そのために、演劇は役に立つ。『#マジゲキ』のように、異なる背景を持った人たちが楽しくコミュニケーションを取れる力が演劇にはあるからだ。
楽しさの核にあるのは、多世代が関わることでの役割分担はあれども「教える、教えられる」の上下関係ではなく一緒に想像力の世界で遊ぶ=創作することだ。
夢中になって遊んだ中で発見したことは一生身体に残る。いつかどこかで、「ああ、マジゲキであんなことあったな」と、関わった人々が思い出すこともあるのではないかと期待する。作品内容やスキルなどの具体的なことはもちろん、チームメンバーと交わした表情や言葉こそが栄養分となって意識的にも無意識的にもこれからの自分を作っていく。
プロジェクト公演が終わっても、ひとりひとりの人生は続く。迷う。悩む。決断する。その人生の過程で演劇が隣にあってもなくても、あの時過ごした演劇の時間、そこでの出会いが自らを支えられたらいい。そんな『#マジゲキ』でありたい。そんなプロジェクト公演をこれからも作っていきたい。
文:中込遊里(演劇ネットワークぱちぱち総合ディレクター)
舞台写真:斎藤弥里
あなたも演劇ネットワークぱちぱちに参加しませんか?
ぱちぱちでは、常時メンバーとスポンサーを募集しています。
演劇に興味のある18歳~25歳の方 ⇒ メンバーになるにはこちら
「あなたにとって演劇とのより良い付き合い方を見つけるための環境作り」に共感する方 ⇒ スポンサーになるにはこちら